はじめに
いつからだろう。「自分がやらなきゃ」と思うようになったのは。
仕事でも家庭でも、頼られることは多い。周りの人に迷惑をかけたくない、期待には応えたい。そんな思いで、気がつけばいつも自分にムチを打っていた。
最初は「やりがい」だったはずのことが、いつの間にか「義務」になっていた。
本当は疲れているのに、それすら感じないふりをして。気づけば、眠れなかったり、朝起きるのがつらくなったりしていた――。
頼まれると断れない、背負いすぎてしまう人へ
責任感があること自体は、素晴らしいことです。けれど、それが「自分の限界を超えてがんばり続けること」と結びつくと、心も体も持ちません。
たとえば、職場で「このプロジェクトは君にしか任せられない」と言われたとき。
本当は手いっぱいなのに、断ることができず、また一つ仕事を引き受けてしまう。
あるいは、家では子どもやパートナーのサポート役として、つねに気を配り、誰かの感情や状況を先回りして動いてしまう。
こうして「やるべきこと」「期待されること」がどんどん増えていき、
いつしか「自分がどうしたいか」「自分が疲れているかどうか」さえ、わからなくなってしまうのです。
「責任感」の背景にあるもの
責任感の強さには、その人の価値観や、生きてきた背景が関係していることがあります。
たとえば、「いい子でいなければ」「ちゃんとしていなければ」と育ってきた人は、
無意識のうちに「誰かをがっかりさせてはいけない」「失敗してはいけない」と、自分を追い詰めてしまう傾向があります。
あるいは、幼い頃に親を助ける立場だった人は、大人になっても「自分ががんばらなければ」という思いを手放せないことがあります。
これは性格の問題ではなく、その人がこれまでどうやって生き抜いてきたか、
何を大切にしてきたか、という歴史の一部でもあるのです。
どこで立ち止まるかは、自分で決めていい
がんばることを否定する必要はありません。
けれど、いつでも全力で走り続ける必要はないのです。
「今日はもうここまでにしよう」
「これは他の人にお願いしてみよう」
「これは、今の自分にはできない」
そう言っていい場面は、きっと今よりもたくさんあるはずです。
むしろ、それを自分に許すことが、長く健康に生きていくためには欠かせません。
あなたの責任感は、きっと誰かの役に立ってきたし、これからもそうでしょう。
でもまずは、自分自身の体と心の声に、少しだけ耳を傾けてみてください。
おわりに
責任感をなくす必要はありません。
でも、「がんばりすぎない責任感」に、少しずつ切り替えていくことはできます。
・「無理せずやる」ことも、立派な責任感です。
・「人を頼る」ことも、チームにとっては大切な力です。
・「今は休む」ことも、次に動き出すための準備です。
どんなに優れた航海士でも、嵐の中ではいったん港に避難します。
あなたの航路が、また穏やかな海へと向かっていけるように――。
この場所が、少しでもそのヒントになれば幸いです。


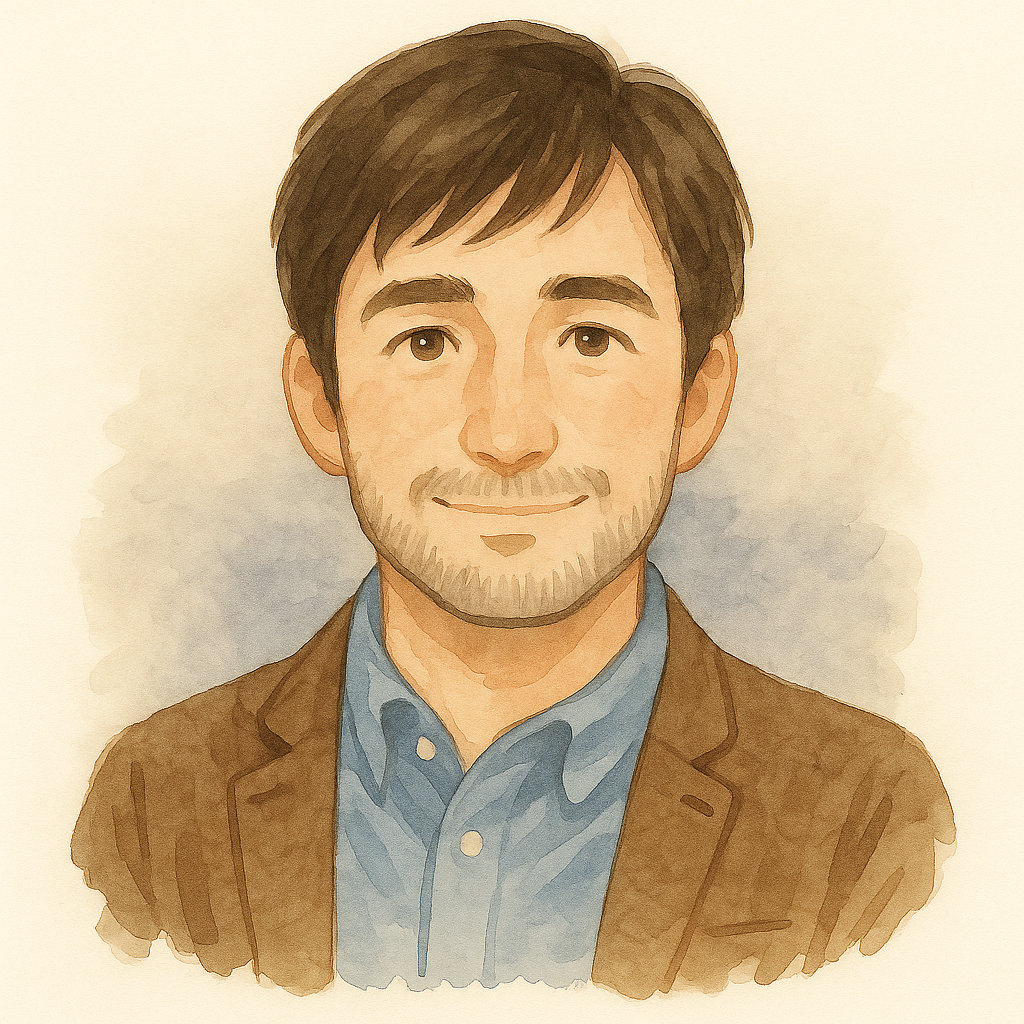
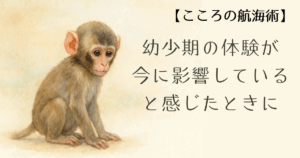
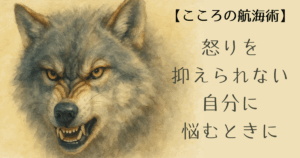
コメント